
相対性理論
相対論を勉強する前に知っておかねばならないこと
時空間について h15.8.16
・4次元時空間の箱は、ニュートンが言ったような完全な直方体なのではなく、アインシュタインが言ったように『時空間は動くと歪む』のだ。
‘動く’時空間というところが少し難しい。動いている座標系でも、瞬間的には止まって見える。止まっているほうが見やすくてわかりやすい。だから、止めて見よう。
・時空間というなにか透明な‘もの’があって、それをものさしで測るのではなく、時空間の中に置かれたものさしじたいが時空間の構造を決定するのだ。つまり、ものさしじたいが時空間なのだ。
昔リーマンが「距離を決めれば空間の構造が決まる」と言ったように、ものさしが距離であり、ものさしが時空間の構造を決めるのである。空間がびっしりものさしで埋まっていると考えればよい。
もっとも、時空間だけが実在する空間のすべてではない。他に、電磁空間や、各素粒子の物質場や、感覚場(私の実在哲学参照)などがある。
4次元時空間 h15.8.17
・アインシュタインの『特殊相対性理論入門』にもあることだが、3次元空間の中に置かれたものさし上の各点に時計を置くと、4次元時空間になる。これだと、3次元空間の中で4次元時空間が見れて便利だ。(いわゆる次元上げの技法)

このように、アインシュタインは初期の頃はじつに天才的だったのだが、売れてからはリーマン空間とか4次元テンソルとか言い出してリコウぶるようになって、ことばがすこぶる抽象的数学的になってわかりにくくなってしまったのが残念である。
長さについて h15.8.27
ものさしは物の長さを測るためにあるのではなく、物の長さを決めるためにあるのだ。
例えば、動いている物体と同じ速さで動いているものさしで測って1mあっても、動いているものさしじたいが(止まっているものさしと比べると)縮んでいるから、動いている物体も同じように縮んでいることになる。
時空間 h15.9.18
時空間というもの(透明な物体)があるのではない。あるのは、時空間のフレーム(枠組み)だけだ。古典力学では、この枠組みは不変だった。アインシュタインが発見したのは、この枠組みが動くと歪むと言うことだ。
時間と空間は現象を記述するときの言葉だ。…(何度も言うが)時空間は物体ではない。
宇宙の姿は、なにもない真空に物質の波があるだけだ。(物質の波の性質は量子力学で勉強しよう。粒子=デルタ波だから、物質はすべて波だ。物質の波の形が時間によって変わるのだ。)
空間・時間について☆☆☆ h16.1.31
時空間は人工の産物であって自然に存在するものではない。時空間は人間が定義してはじめて存在し得るのであって、はじめから存在しているのではない。つまり、時空間は実在しない無限に細い線から出来ている4次元の格子(枠組み)自体であって、その中で実在する自然現象が記述されるのである。(時空間の4次元性も、人間が決めた時空間の定義からの帰結である。)
このように概念が実在的であろうがなかろうが、人間が(とくに自分が)決めた概念で実在を見て行くことが、現代科学のあり方・やり方である。“空間(距離)”の概念はそもそもデカルトが近代において自分で定義した概念(言葉)であって、人間が1mの長さを決めたから物の長さや物の位置が決まるのであり、人間が1mの長さを決めなければ物の長さや物の位置もないに等しいのだ。“変形する時空間”が、相対論が新たに導入した概念であり、この概念で自然を見て行くと自然がうまく理解できるのだ。そういう意味で、“変形する時空間”は実在的な概念であるといえる。
ニュートンは時空間を自然にあるものと考えていたが、アインシュタインは人が自分で定義して創り出した言葉であると考えた。その言葉を使って人は自然を見るのだ。時空間の言語性こそがアインシュタインの鋭い洞察である。そもそも、カントが時間・空間が言葉であることを見抜いていたが、見るものだけについて考えて見られるものについて考えなかった、つまり言葉と実在とを結び付けなかったので、相対論のような発展がなかった。
実在しない時空間において実在する自然現象を記述することによって、時空間と現象との間に関係が付く。さらに、同じひとつの自然現象を異なるふたつの時空間が測定することによって、ふたつの時空間の間に関係が付く。(自然現象を記述する言葉としての)実在しない時空間が実在する自然現象を介して関係付けられるのだ。その関係が光速度不変の原理によって結ばれているものが特殊相対性理論である。相対論では、ローレンツ変換で空間と時間とが混ざり合う(空間と時間が同質!)ので、空間と時間を切り離さずにひとつにして時空間と呼ぶのである。
『時空間は言葉であって物ではない。』から、同じひとつの現象(実体)をふたつの異なる観測者(時空間)からながめることになる。その際、時空間が観測者によって異なるので、同じひとつの現象についても長さや時間が違ってくる。
長さとは何か? h16.2.1
だれか(クーベルタン男爵?)が長さの単位(1m)を決めた(定義した)から、その単位長の何倍あるかによって物の長さが決まるのであって、長さの単位を決めなければ、物の長さなど存在しないのだ。この意味で、物の長さは自然にあるものではなく、人間が(長さの単位を定義することによって)創り出したものだと言える。
長さじたいが何かは人知を超える問題なので、考えないことにする。それはギリシア人の問題であって、いくら考えても時間の無駄になるだけだ。だから、まず、長さがあることを認めるのだ。わからないことを考えないことが、わかるコツだ。(実在哲学においても、感覚がなぜ脳細胞の興奮で発生するかはわからない。とにかく脳細胞の興奮で感覚が発生することは事実だから、それを認めることによって視野が拓けるのだ。そもそも、力学においても、なぜF=maが成り立つかつまりどうして物体に力が働くと加速されるかはわからない。でも、それを認めることで実在が理解できるようになるのだ。つまり、原理とは理解できないことなのだ。理解できないことを原理に押し込むことで、理解できる世界が拓けるのだ。理論とはそういうものだ。)
時間とは何か? h16.2.1
これも長さと同様に、誰かが時間の単位(1秒)を決めたから現象(例えば、学校が始まってから終わるまで)についての時間が単位時間の何倍あるかによって決まるのであって、単位時間を決めなければ現象についての時間など存在しないのだ。つまり、時間の単位を決めない場合、学校が始まってから終わるまでの一連の現象があるだけで、その現象についての時間は考えられないから時間は存在しないわけである。そういう意味で、時間は自然にあるものではなく、人間が(単位時間を定義することによって)創り出したものだといえる。
時間自体が何かは、これまた人知を超える問題なので考えないことにする。それをやると、昔のギリシア人のように泥沼にはまる。とにかく時間という量があることを認め、あとはそれを測ることだけ考えればよい。それが限りある知性を持った人間としての立場だ。
言葉としての時空間☆ h16.2.1(私の数学アラカルト『連続体仮説』参照)
時空間は、実在の中で起こる現象を記述するために人間が創り出した言葉であって物ではない。いわば、時空間の枠組みの中に実在する宇宙を放り込んで宇宙を観察するのであって、宇宙の中に時空間の枠組みが埋まっているのではない。だから、時空間の枠組みは観察者の数だけ無数にあるし、人の創造物(想像の産物)だから伸縮自在であってもいい(相対論)。
聖書でも『はじめに言葉ありき。』と言うではないか。神は言葉(つまり、4次元時空間)のあとに実在する宇宙を創造されたのだ(冗談)。
哲学×数学×物理学=相対論 h16.2.8
哲学者は認識する者だけについて考えて、認識される物については考えなかった。
時間・空間が言葉であることはわかっていたが、光速度不変の原理は知らなかった。
数学者は静止しているものしか理解しない。
リーマン空間までわかっていたのに、“動く座標系”が思いつかなかった。
物理学者は、認識される物については詳しいが、認識自体(つまり哲学)には無知だった。
時空間を実在するもの(透明な物体)だと考えていた。
哲学と数学と物理学の知識(と言うかセンス)が全部そろってはじめて相対論が理解できるのだ。
一般相対性理論 h16.2.8
動く慣性系の時空間が歪むのなら、逆に歪んでいる時空間は動く慣性系だと考えられる。このように、動く慣性系と時空間の歪みとは同値である。
動く慣性系⇔時空間の歪み
同値
(動く慣性系の速さは時空間の歪みの程度で、動く慣性系の動く向きは時空間の歪みかた(+VかーVか)で区別できる。)
少しずつ歪み[ゆがみ]が違う時空間が隣接して分布している場では、静止している質点に加速度が生じ、(ma=Fより)力(重力)が働く。

ある地点に置かれた(無限遠点から見て静止している)質点は、その地点にある慣性系(いわゆる局所慣性系というエレベーター)に乗って見ると、慣性系(エレベーター)の走行と反対向きに速さvで動いているように見える。つまり、質点は速さvで落下している。次に、質点が隣接する慣性系に移ると、別の速さv’で落下する。v’>vだから、質点は加速される。これが重力の正体だ。
1)光の青方・赤方偏位
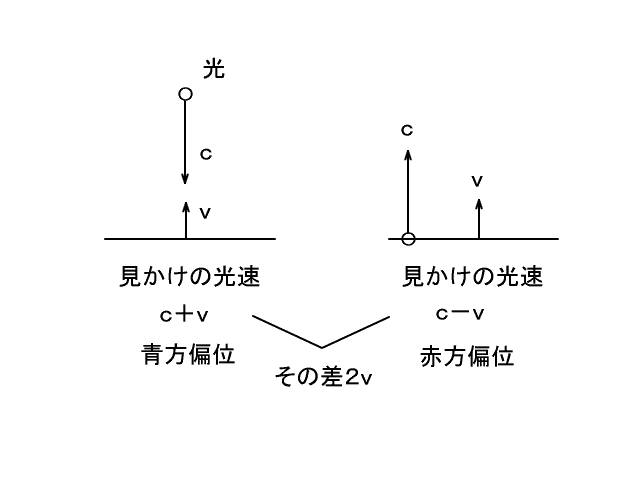
地上における慣性系は鉛直上方へ速さvで動いている。
一方、光速cは光速不変原理によって変わらない。
2)重力レンズ
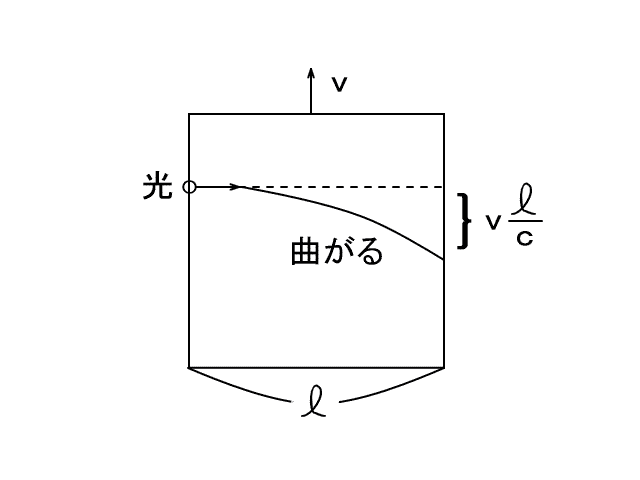
3)水星の近日点移動
上の光を質点(水星)に置き換えればよい。つまり、
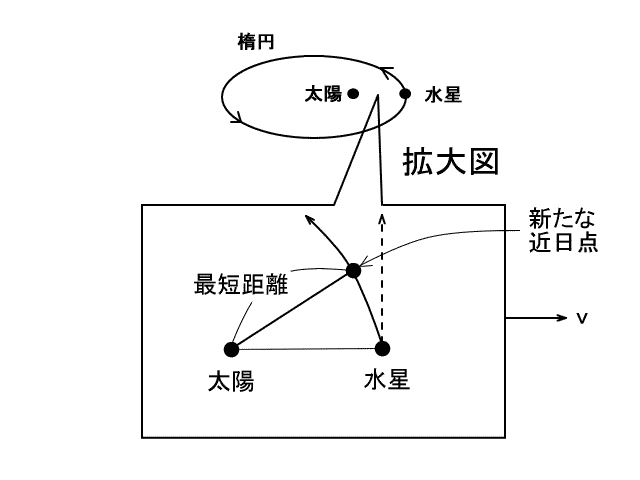
なぜ地上では身体が重力を感じるのか? h16.2.9
(自分や他人の)身体は実在する物体である。
身体の運動を問題とするとき、身体の周りに(局所)慣性系(座標系)をとって考える。この慣性系(座標系)は言葉であって物ではない。つまり、物体の位置や時間を測るために人間が自分で考え出した実在しない無限に細い棒(格子)であって、はじめから実在の中に埋まっていて、それを人間が掘り出したのではない。
一般相対性理論では、いったん重力を無視することにする。座標系の歪みだけから重力を新たに作り出すのだ。
いま身体が空中に浮かんでいて、無限遠から見て静止しているものとする。(文字通りの‘地上’では、地面からの反作用があるので考えにくい。)
地上における身体の周りの座標系は、無限遠の宇宙(歪みのない空間)から見ると歪んでいて、鉛直上方に動いている。つまり、(無限遠から見て静止している)地上にある身体は(地上の局所座標系から見ると)座標系と反対方向すなわち鉛直下方に動いている。したがって、(身体の周りの慣性系から見ると)Δt秒後の身体の位置は鉛直下方-vΔtにある。(身体の周りの慣性系から身体の周りの慣性系を見ると、身体の周りの慣性系はそれ自身を見ることになるので、もとの位置にとどまっている。)ところが、下にある座標系のほうが(無限遠の宇宙から見て)歪みが大きく、座標系はより速いスピードで鉛直上方に動いているから、身体はその分速く鉛直下方に動くことになる。したがって、速さの差だけの加速度が身体に働くことになり、身体は(身体の質量)×(加速度)分だけの慣性力すなわち重力を感じることになる(昇りのエレベーターに乗ったとき、身体が重くなるのと同じ理屈)。【数量的に細かいことは専門書をお読みください。】
時空間の任意性 h16.2.9
時空間は言葉であって物ではない。
したがって、伸びたり縮んだり歪んだり捻ったり捩ったり捻じ曲げたり裏返したり引っ繰り返したり穴あけたり埋めたり千切ったりくっ付けたり拡大したり縮小したり(ありったけ考えられること)…なにをやってもいい。
ただし、いくら言葉とはいえいくつかのルールがある。一様な場での平行移動における不変性とか、光速不変原理とか…。
それを守るかぎりは、なにをしてもいい。
量子力学も、この調子で理解できないものか。こうして見ると、量子時空間(時空間をマス目に区切って、その中では位置や時間の区別がないとすること)も一概には笑えない。物ではなく時空間のほうをいじる(改良する)ことによって問題を解決する相対論と同じやり方だ。シュレーディンガーは質点に波動性を入れることによって、つまり物のほうをいじることによって2重性の問題を解決した。量子時空間では、質点はいじらずに時空間のほうをデジタル化する(量子化する)ことによって同じ2重性の問題を解決した。ほかに、分裂する時空間を考えるやり方もある。これも相対論かぶれだ。物理現象は時空間と物との兼ね合いなので、どっちでもいい。しかし、アインシュタインは言った。「シンプルなほうが正しい」と。
北村のプリント(知らない人は無視してよい。) h16.2.9
現代物理では、力に対する2つの考え方がある。
1)『力は時空間の歪みである。』
正確には、力は異なる歪みを持った時空間連続体であると言うべきであろう。相対論によって導入された考え方だ。
2)『力は素粒子が荷っている。』
これは、そのまま正しいだろう。例えば、電気力は光が、核力は中間子が荷っているのだ。エネルギーに最小単位があるので、粒子が荷っていると考えたのだ。(実在哲学では、感覚は興奮した脳細胞が荷っていたが。)
ついこの前まで、私は2が1をただ量子化しただけのことだと思っていた。つまり、時空間の歪み方がジワーと連続的にずれずにガクッガクッと飛び飛びで量子的にずれるものだと思っていた。
しかし、実はそうではない。物理現象は物と時空間の兼ね合いで成り立つのであり、1では力の原因を時空間(言葉、見るもの)のほうに、2では物(見られるもの)のほうに帰着している。まったくの別事なのだ。
1と2が統合されるのはいつの日のことだろうか。重力ならグラビトンが荷っていると考えてもいいし、時空間の歪みと考えてもいい。たしかに、重力の場合、時空間の歪みは量子化されるのだ。つまり、もの(物質、素粒子)とこと(言葉、時空間)とが統一されるのだ。(実在哲学の場合でも、感覚を荷う素粒子(感覚子)を考えることによって、こととものとが統一された。)
まとめ)『現象=もの(実体)×こと(時空間)』だから、現象としての力の原因には、ものとことのふたつある。ものとしては素粒子。こととしては一様でない時空間の歪み。
相対論に対する感想 h16.2.9
相対論は時空間の力学(運動学)であって物質の力学ではない。
そういう意味では、物理学よりもむしろ哲学に近い。
哲学の中に数学を持ち込んだようなものだ。
さすがにドイツは哲学の国だ。
すると物理学はイギリスの伝統芸か。
ドイツでは物理現象を見るもの(時空間)と見られるもの(物体)との兼ね合いで捕らえているが、イギリスでは見られるものしか考えない。(実在哲学でも、認識は物と感覚の兼ね合いで決まると考えている。同じ物でも知覚で見るか、五感で見るか、心で見るかによって認識が違ってくるのだ。)
それにしても、ドイツ人は光が好きだ。光って、いったい何なんだ?!
とにかく、「動く時空間は歪む」アイデアによって、これまでの物理学では見えなかった世界(実在の部分)が見えるようになったのはめでたい。
ブラックホール h16.2.13
光の赤方偏移の極端な場合を考える。
今惑星の質量が極端に重い場合を考えると、惑星の周りの時空間の歪みが大きくなり、ついには惑星の周りの慣性系の速さが光速を超えるようになる(v>c)。(慣性系の速さは光速を超えてもかまわない。なぜなら、慣性系は言葉であって物ではないからである。)すると、惑星の中心から出た光は惑星の外に出られなくなる。たとえ、軽い惑星でも、惑星の中心に近づけば時空間の歪みは大きくなるから、原理的にはブラックホールである。慣性系の速さが光速を超える限界線をシュバルツシルド半径または時空の地平線と言う。
天動説と地動説 h16.2.14
選択する理論によって見えやすい現象が変わる。
問題によっては天動説を選んだほうがいい。
自転車や自動車を運転するときに、いちいち地球の自転や公転を考慮する必要はない。それでは、かえって複雑になり混乱する。
日常生活の大部分の問題が天動説のほうが解き易い。
自分が取り扱う問題が最も解きやすくなるように、理論体系を構築・選択すればよい。
例えば、自転車や自動車の運転には、相対論よりもニュートン力学が、地動説よりも天動説が適している。
重力レンズも水星の近日点移動も自分の日常生活においてはまったくドーデモイイコトである。そんな知識は知ったところで何の役にも立たない。だから要らない。紙の上だけのドーデモイイ勉強ばっかりしているから、センスが悪くなる。
それより、自分の日常生活の中に横たわる問題を解決できるようなものの見方を習得したほうがいい。
他人の道(人生)と自分の道は違うのだ。他人の書いた本を読むより、自分の道の上に転がっている問題を自分で考えたほうがいい。
時空間の言語性 h16.4.1
時空間が実在する宇宙の性質であるとすると、宇宙には唯一の時空間があることになる。しかし、これは間違いである。
時空間が人間の作った言葉であるがゆえに、時空間には優劣の区別がなく、したがって相対性原理が成り立つことになる。
等価の原理 h16.4.4
重力がある場でも、座標系の取り方によっては、無重力空間にできる。
このことは、宇宙空間が本来無重力空間であり、重力は人間の作った(言語としての)時空間の歪み(正確には、少しずつ歪みの強さが違う時空間の連続体)として捉えればよい(考えればよい、見なせばよい)ことを意味している。
時空間すなわち座標系において実体(実在)を見ることは、座標系(言葉)と実体(物)との間に関係をつけることであり、そうすることによって座標系(言葉)が実在(物)によって規制を受けることになる。つまり、重力のある場では(言葉としての)時空間は歪まなければならない決まりがあるのだ。光速度不変の原理により動いている座標系が歪まなければならないように、質点(質量)の存在によって座標系が連続的に歪まなければならないのである。
違う歪みを持った時空間が連続に分布していると重力があるのと‘同じことになる’というのが、‘等価’の原理だ。
言葉としての時空間をいろいろいじることによって(物と言葉の相互作用としての)物理現象を説明するのが、相対論が産み出した新しいアイデア(世界観、方法)だ。
タイムマシンの原理(SF) h16.4.24
超伝導のマイスナー効果のように、物体内部に時空間が入り込まなければ、その物体は時空間の外に出たことになり、物体が時空間の外を移動して再び時空間の中に戻れば、任意に時空間を移動することができる。ただし、その物体の一部に時空間を取り込んでいないと、タイマーが効かなくなり、Dr.スランプの‘時間よ止まれマシーン’のようになってしまう。
物体内部に時空間を入りこまさない方法としては、
1)超伝導体のマイスナー効果のように、物体を特殊な状態にして物体内部の時空間を外部に弾き飛ばす。
2)一般相対性理論の時空間と電磁場の相互作用の式を利用して、高エネルギーの電磁場によって時空間を制御する。
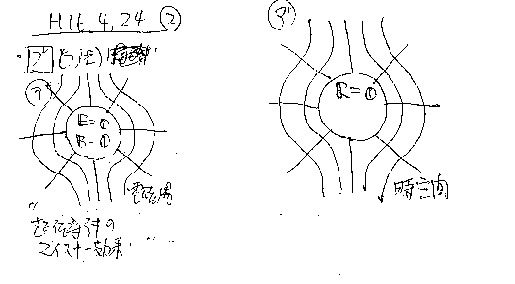
ワープエンジンの原理 h16.5.9
光速を突破するには、∞の出力が出るエンジンを作ればよい。エンジンの出力解が∞になるようなエンジンを作ればよい。光速が出せれば、宇宙の端から端まで瞬時に行ける。〔スタートレックのワープエンジンはロケットエンジンを超える準光速を出せる高出力エンジンのことなのだろう。たとえ光速以下でも光速に近づけば時間の経ち方が遅れるから、どこまでも遠くへ行くことができる。〕
現代物理学の原理 h17.9.15

宇宙を、空間・時間の属性のある空*間と、空間・時間の属性のない一点から成る素粒子に分けて考える。(有と無の間に空があり、空は無ではない。本当は‘*’を‘空’の斜め右上に書きたかったのだが、ソフトウェアの制約上、‘空’と‘間’の間になってしまった。)
逆に、空*間と素粒子が混じりあって宇宙が出来ている。
空*間の性質は、有としての素粒子を空*間の中で動かして見ることによって捉えられる。
その結果、空*間には相対性とか不確定性とかの性質があることがわかった。
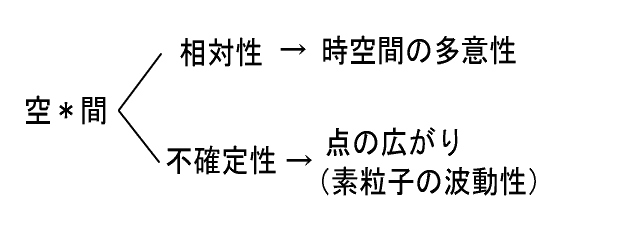
△観測問題 h17.9.15
観測には、固有値の観測と非固有値の観測の2種類がある。
固有値の観測では、対象の状態は変わらない。
非固有値の観測では、逆さにしたコップの中の水が撒き散るようにランダム化が起こり?(そしたら、ランダム化はどうして起きるのか??)、対象の状態が観測量の固有状態のどれかに変わり、その物理量の値をとる。
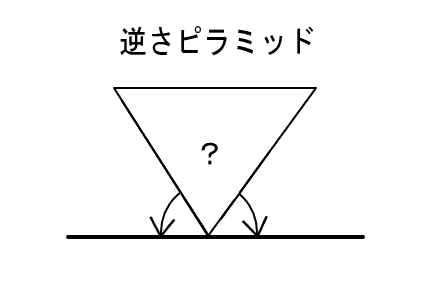
(補足)相対論に幅を利かすとボルンの原理のように状態のジャンプ(不連続的変化、つまりシュレーディンガー方程式の否定・逸脱)を認めねばならないが、
相対論を部分的に否定すれば(つまり、光速を超える状態の変化を許せば)シュレーディンガー方程式が復活し、観測(原理的には素粒子と素粒子の反応)が連続的変化として捉えられる。
相対論は絶対的なものではなく、場合によっては成り立たないこともある(例、EPRパラドックス)。
ユークリッド幾何学 h17.9.15
ユークリッドの5公準で定義付けられた(構成された)『ユークリッド空間』についての性質を調べる学問。
ユークリッド空間についての学問(研究)だから『ユークリッド空間学』と言うほうがふさわしい。
ユークリッド空間の性質を調べるために考え出されたのが、点とか線とか角などの概念である。
ところで、われわれの住んでいるこの宇宙の空*間はユークリッド空間でないどころか、相対性や不確定性までも蔵している複雑な空間である。
エーテル h17.9.18
時空間が寒天のような物体であるとすれば、寒天が有機分子が絡み合って出来ているように、時空間も何かの原子(エーテル原子)から出来ていると考えられる。
デカルトはエーテル原子に穴が開くことによって、物体は隣の位置に移動できると考えた。エーテル原子はその物体が動いた後の穴を埋めるから、したがって惑星は円運動せざるを得ない[渦動説]。
デカルトは無限直線運動を見落としていたのだ。